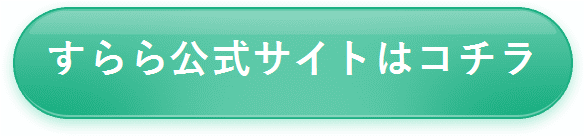すららは不登校でも出席扱いになる?なぜ?出席扱いになる理由について
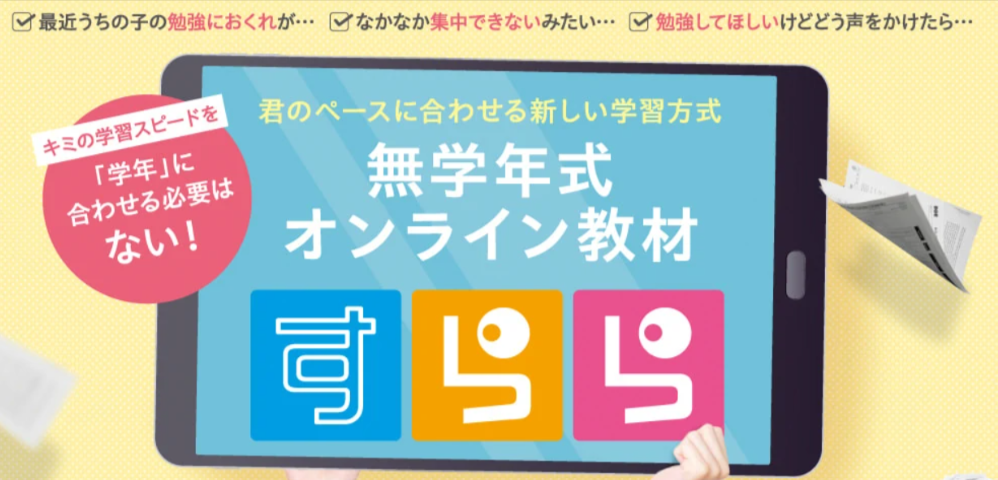
不登校で学校に通えなくなった子どもにとって、「家庭学習が出席扱いになるかどうか」は、学力維持だけでなく心の安定にも大きく関わります。
文部科学省では一定の条件を満たせば、家庭での学習も「出席扱い」として認定できるガイドラインを示しています。
すららは、その条件に対応できる教材のひとつとして多くの自治体・学校で導入されてきました。
ここでは、なぜすららで学ぶことで出席扱いが可能になるのか、5つの理由をわかりやすく紹介していきます。
ご家庭で安心して取り組むためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららでは、学習内容・学習時間・正答率などのデータがすべて自動で記録されます。
これにより、「今日は何をどれだけ勉強したのか」「理解度はどれくらいか」といった客観的な学習の質が、保護者の手間をかけずに可視化される仕組みになっています。
すららは学校向けに提出できる「学習記録レポート」もフォーマット付きで用意されているため、学校側からも“ちゃんと取り組んでいる”という証明として受け入れられやすいのが特長です。
不登校中でも、しっかり学習していることが伝わることで、出席扱いへのハードルがぐっと下がります。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららは、子どもが取り組んだ内容をすべてシステム上で記録し、まとめてレポートとして出力することができます。
このレポートは、日付・学習単元・得点率などが明記されており、学校側にとっても「学習の証拠」として非常に信頼性が高いものです。
手書きや口頭での報告では信頼を得づらい場合でも、このような客観的なデータがあれば出席扱いとしての認定がスムーズになります。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
毎日学習の記録をつけたり、先生に進捗報告をするのは保護者にとって大きな負担ですが、すららならその必要はありません。
全ての学習ログはシステム上に自動保存され、保護者はいつでも確認できます。
学習の「見える化」がされていることで、学校側も安心して出席扱いを判断しやすくなります。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
すららでは、ただ教材を提供するだけでなく「すららコーチ」という専任の学習サポーターがついて、学習計画の作成から進捗の確認、モチベーション維持までをトータルで支援してくれます。
これにより、ただ自宅でダラダラと学ぶのではなく、“目的を持って計画的に学ぶ”姿勢が自然と身につきます。
また、無学年式のため「戻って復習する」「得意科目だけ進める」といった自由度の高い学習が可能。
こうした個別最適な支援と継続性の高さが、出席扱いに繋がる重要なポイントになります。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
計画を立てても子どもが続けられない…そんな心配も、すららなら安心です。
コーチが定期的に状況をチェックし、必要に応じて計画の見直しも提案してくれるため、「ちゃんと続けられる仕組み」が整っています。
これが学校からも評価される要因のひとつです。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
子ども一人ひとりの特性に合わせて、無理のない学習計画を立ててくれるのがすららのコーチ。
とくに不登校の子どもにとって、「やりすぎず、でも続ける」バランスを取ってもらえるのは大きな安心材料です。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
小学校低学年の内容に戻ってやり直すことも、中学生内容を先取りすることも自由自在。
無学年式の柔軟な設計があるからこそ、子どもが自信を取り戻しながら学ぶことができ、出席扱いの根拠にもつながります。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
不登校の出席扱いは、「家庭」と「学校」の信頼関係がカギです。
すららでは、その橋渡し役としてコーチがレポート作成や書類提出のサポートまで行ってくれます。
どの書類が必要で、いつ・誰に提出するのか?という情報も丁寧に案内されるため、初めて出席扱い申請をするご家庭でも安心して手続きが進められます。
また、学校の先生とやり取りする場面でも、「すららを使っている」と伝えるだけで理解を得やすいのは、全国の学校との連携実績があるからこそです。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
書類提出って意外と手間がかかりますよね。
でも、すららなら「どこに何を出せばいいか」までしっかり案内してくれるので、不安を感じずに進められます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
出席扱いを学校に申請するには、「学習記録の提出」が必須になります。
しかし、保護者だけでそれを用意するのはなかなか大変です。
すららでは、専任コーチが学校に提出するための学習レポートのフォーマットを準備してくれたり、記載すべき内容についてもアドバイスをくれます。
実際のフォーマットには、学習時間・学習内容・正答率・継続日数などが整理されており、学校側にとっても確認しやすい形になっています。
保護者が自分でゼロから資料を作る必要がないので、手続きに不安があるご家庭でも安心して進めることができます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
「学校と連絡を取るのが緊張する」「担任や校長先生にどう伝えればいいか分からない」…そんな悩みを抱えるご家庭は少なくありません。
すららでは、担任や校長先生との連絡がスムーズにいくよう、文面例の提供や会話のポイントまでアドバイスしてくれることがあります。
また、コーチが出席扱い制度や学習内容について保護者と一緒に整理してくれるので、自信を持って学校に説明できるようになります。
家庭・学校・教材がつながる体制こそ、すららの大きな強みです。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、不登校の子どもたちの学びを支える「出席扱い可能な教材」として、文部科学省のガイドラインに対応した内容になっています。
実際に、全国の多くの教育委員会や学校現場で正式に導入されており、すららを使った学習が“出席扱い”とされた事例は多数あります。
このような実績があるからこそ、学校側も「すららなら安心して認められる」と判断しやすく、保護者にとっても信頼できる選択肢になっているのです。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは単なる民間教材ではなく、教育委員会や学校と連携しながら導入された実績が豊富にあります。
特に地方自治体によっては、不登校支援や家庭学習支援の一環として公式に推奨されているケースもあります。
こうした“公共機関との信頼関係”が築かれているからこそ、学校側もすららを使った学習を前向きに受け入れてくれやすいのです。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、教育現場で「不登校支援教材」として広く認知されています。
文部科学省の資料でも出席扱い制度の対象となるツールとして名前が挙がるほどで、その信頼性は折り紙付きです。
実際に「出席扱いとなった成功例」も多数あり、そのノウハウも蓄積されています。
ただ勉強するだけでなく、「制度を活用しやすい仕組み」が整っているのが、他教材との大きな違いです。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いになるかどうかの大きなポイントのひとつが、「その学習環境が学校に準ずるものかどうか」です。
すららは、国語・数学・理科・社会・英語など、学校の主要5教科をカバーしており、すべて学習指導要領に準拠した内容になっています。
また、ただ学習するだけでなく、その成果を可視化し、フィードバックする機能も充実。
これにより、「家庭学習でも学校と同じように学習効果がある」と判断されやすくなっているのです。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららで扱う教材は、すべて文部科学省が定める「学習指導要領」に対応しており、小学生〜高校生までの内容がしっかりと網羅されています。
教科書内容に準じたカリキュラムになっているため、「学校の代わりになる教材」としての信頼性が高く、校長先生からの理解も得やすい設計です。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
学習効果を“見える形”にすることは、出席扱いの判断材料として非常に重要です。
すららには、問題演習の結果や正答率、単元ごとの理解度などをグラフ化してくれる機能が備わっており、「いつ・どの教科を・どのくらい学習したか」を一目で確認できます。
また、コーチからのフィードバックがあることで「評価・アドバイス」という学校と同じプロセスが実現でき、安心して報告書類を提出できます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法の流れ紹介
不登校のお子さんを持つ保護者の方にとって、「自宅での学習が学校の出席扱いになるのか?」はとても大きな関心ごとです。
文部科学省は、条件を満たした家庭学習であれば「出席扱い」にできると明確に示しており、すららはその条件を満たす教材として多くの実績があります。
とはいえ、出席扱いを受けるには学校との連携や書類提出など、いくつかの手続きが必要になります。
ここでは、その具体的な申請方法と流れについて、4つのステップに分けて丁寧に解説していきます。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱いを希望する場合、まず一番最初にすべきことは、担任の先生または学校に相談することです。
どんなに良い教材を使っていても、学校側が出席扱いとして認めなければ制度は適用されません。
できれば面談などの形で、子どもの現状や家庭学習の様子を共有し、「出席扱いを受けたい」と伝えるのがベストです。
担任や校長先生にとっても、早めに状況を知っておくことで、今後の判断がしやすくなります。
最初の一歩を遠慮せず、丁寧に伝えることが大切です。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
担任や学校と話をしたら、次に確認すべきは「必要な書類」と「満たすべき条件」です。
すららを使っている場合、学習記録の提出や継続学習の証明が必要になります。
あわせて、申請書のフォーマットや、学校が独自に求めている内容があるかもチェックしておくと安心です。
学校によって判断基準や提出書類の種類が若干異なるため、事前確認が出席扱い成功のカギとなります。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の理由が「情緒的な不安」「身体的不調」「発達障害」など医療的な背景を伴う場合、医師による診断書や意見書が必要になるケースがあります。
これは、学校側が「家庭学習での継続が妥当である」と判断する材料として求められることがあるからです。
ただし、必ずしも全員に必要というわけではなく、状況によっては求められないこともあります。
診断書が必要な場合は、あらかじめ医療機関での受診を準備しておくとスムーズです。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
学校側は、「なぜ登校できないのか」を明確に理解するため、医師の所見を必要とすることがあります。
とくに精神的な理由や発達障害による不登校では、診断書の有無が判断材料になることも。
学校との話し合いの際に、必要書類について具体的に確認しておきましょう。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書を依頼する際には、「不登校の状況」だけでなく、「家庭学習の継続が望ましい」という文言を含めてもらうと、学校側も出席扱いを判断しやすくなります。
受診時には、学校に提出する目的であることを医師に伝え、すららを使った学習の様子などもあわせて相談してみましょう。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららを使っている最大の強みは、「学習記録が自動的に残ること」です。
日々の学習時間や内容、正答率などが記録され、レポートとして出力することができます。
これを学校に提出することで、「家庭でもしっかりとした学習が行われている」と証明できるのです。
保護者の手間も最小限で済むうえ、学校側からも客観的な証拠として信頼されやすいポイントです。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららでは、学習履歴を「レポート形式」でPDF出力できます。
学習日、時間、理解度などが一目でわかる形式になっており、これを印刷して担任や校長先生に提出することで、申請書類として活用可能です。
提出頻度や範囲については、学校と相談して決めると良いでしょう。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
多くの学校では、「家庭学習を出席扱いにするための申請書」のフォーマットがあります。
保護者は子どもの学習状況や体調などについて記入し、学校側に提出します。
場合によっては、担任と一緒に記入内容を相談しながら進めるケースもあります。
初めての方は、すららのコーチやサポートからアドバイスを受けながら準備を進めると安心です。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
すべての書類が揃ったら、最終的に学校長の判断で「出席扱い」として承認されるかが決まります。
ここで大切なのは、家庭での学習が「教育的に有効」であると認められるかどうかです。
場合によっては、教育委員会にも書類が提出され、最終承認を得る流れになることもあります。
学校側との連携を密にしながら、スムーズに進めていくことが大切です。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
出席扱いの最終決定は、原則として学校長の判断によります。
提出書類や日々の学習状況、医師の所見などをもとに、「この子は家庭で継続して学習しており、出席扱いが妥当である」と判断されることで、正式に承認されます。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
地域によっては、学校長の判断だけでなく、教育委員会の承認が必要なケースもあります。
その際は、学校が教育委員会とやり取りしてくれますが、保護者も必要に応じて協力する姿勢が大切です。
書類提出の期限や内容などを確認しながら、学校と二人三脚で進めていきましょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて解説
不登校のお子さんにとって、「出席扱い」が認められることには、学力面だけでなく精神面・将来設計にも大きなメリットがあります。
ただ自宅で学習するだけでは「欠席」と記録されてしまいますが、すららのような教材を使って学校の承認を得られれば、それが「出席扱い」として正式にカウントされるのです。
この記事では、出席扱いを受けることでどのような恩恵があるのかを、3つの視点から解説していきます。
お子さんの未来と、ご家族の安心感に直結する重要なポイントばかりですので、ぜひ参考にしてみてください。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
不登校が続くと、出席日数の不足が原因で内申点に影響が出てしまうことがあります。
特に中学生・高校生の場合は、定期テストの成績だけでなく、日々の出席状況が成績評価に直結します。
しかし、すららでの家庭学習が「出席扱い」として認められれば、学校側の評価にプラスに働く可能性があります。
学習の継続性が担保されていると判断されることで、通知表や内申点への影響を最小限に抑えられるのです。
将来的に進学を考えているご家庭にとって、この点は大きな安心材料になるでしょう。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
内申点は出席状況に強く影響されるため、「欠席が多い=評価が下がる」と見なされることも少なくありません。
しかし、すららを使って学んでいることが出席扱いとして認められれば、その日数が記録され、評価の土台が守られます。
出席日数が一定数確保されることで、真面目に取り組んでいる姿勢が学校側にも伝わりやすくなるのです。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席扱いが認められることで、内申点のダウンを回避できれば、将来の進学先の選択肢も広がります。
全日制高校を含め、多くの学校では内申書を重視するため、出席日数が大きく響きます。
逆に出席日数が十分であれば、「不登校だったのに内申がしっかりしている」という評価を得ることも可能になるのです。
受験に向けた安心材料として、大きなメリットと言えるでしょう。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校になってしまうと、親子ともに「勉強が遅れているのでは」「もう取り戻せないのでは」といった不安に襲われることが多いです。
しかし、すららのような無学年式の教材を使えば、自分のペースで「戻る・進む」が自由にできるため、授業に遅れる心配がぐっと減ります。
これにより、「何もしていないわけじゃない」「ちゃんと学べている」という安心感が生まれ、子どもの自信にもつながります。
出席扱いという形でその学習が認められれば、なおさらその効果は高まります。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららは、1日15分〜30分程度の短時間学習でも効果が出やすい設計になっており、無理なく毎日続けられるのが特長です。
学年に縛られずに、自分が分からない単元にさかのぼって学び直せるため、「学校の授業に追いつけない」という焦りから解放されます。
これにより、精神的な余裕が生まれ、安定して学習が継続できます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
不登校になると、「自分はダメなんだ」と感じてしまう子も多いですが、すららでの学習が評価され、出席扱いとして学校から認められることで、「自分はちゃんとやってる」「認めてもらえた」という成功体験になります。
こうした経験が、子どもの自己肯定感の低下を防ぎ、将来的な学校復帰や社会参加への第一歩になることもあるのです。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校になると、子ども本人以上に心を痛めるのが保護者です。
「このままで大丈夫だろうか」「勉強は遅れていないか」「進学できるのか」など、毎日が不安の連続になります。
しかし、すららのような教材を使って家庭学習を継続し、それが出席扱いとして認められることで、「このままでもちゃんと評価される」という安心感を得られます。
また、すららには専任のコーチがついており、親だけで学習を管理しなくてもいい点も、心の余裕を生む要素となっています。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららの最大の魅力のひとつが、保護者・学校・コーチの“三者連携”が取れるところです。
コーチが学習の進行を見守り、学校には学習記録を提出し、保護者は必要に応じてサポートする。
このように、親がすべてを背負い込まなくてもよい仕組みがあるからこそ、家庭全体の心の安定につながります。
「私一人ががんばらなくてもいい」と思えることが、親にとって最大の救いとなるでしょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための重要な注意点について解説
すららを活用して家庭で学習を続けていても、「出席扱い」を確実に得るためには、いくつかの注意点があります。
文部科学省が示している出席扱い制度には一定の条件があり、それを満たすためには、学校との連携、必要書類の準備、学習内容の整合性など、保護者側も意識して動くことが求められます。
ここでは、実際にすららで出席扱いを申請する際に見落としがちなポイントや、事前に知っておくべき大事な注意点を3つの柱にまとめてご紹介します。
少しでもスムーズに手続きを進められるよう、ぜひチェックしてみてください。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いの可否を決定するのは学校長であり、その判断には担任や学年主任、教頭など学校全体の協力が欠かせません。
すららは文部科学省のガイドラインに準拠した教材ではありますが、すべての先生がその内容を詳細に把握しているわけではないため、こちらから丁寧に情報を提供する必要があります。
特に「家庭学習の質がどの程度か」「本当に継続できているか」といった点を学校側が納得しやすいように、資料や実際の学習レポートを見せながら説明することが大切です。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
出席扱い制度の根拠となる文科省の通知文や、すららがそれに沿って構成された教材であることを、保護者自身の言葉でしっかり説明できるようにしておくことが重要です。
すらら公式サイトや学習記録の出力例を印刷しておき、具体的にどんな学びが行われているのかを可視化して伝えると、学校側も安心しやすくなります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
担任の先生にだけ説明しても、決裁権のある校長まで話が届かないことがあります。
可能であれば、最初から校長や教頭先生にも一緒に相談するようにし、学校全体としての理解と協力体制を築いていきましょう。
すららがどのような教材かを示すパンフレットやレポートは、説得力を増す有効なツールです。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の理由によっては、家庭学習の正当性を証明するために医師の診断書や意見書が必要になることがあります。
特に情緒面や精神的な理由で通学が困難な場合、第三者である医師の見解は学校側にとって非常に大きな判断材料になります。
単に「休ませている」のではなく、「専門家の判断を得たうえで家庭学習を継続している」という姿勢を見せることで、出席扱いとして認めてもらえる可能性が高まります。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
学校側は、「家庭学習が妥当かどうか」「本人の健康状態が学習を続けるのに問題ないか」といった点を客観的に判断する必要があります。
そのため、診断書の有無は申請の成否に大きく影響することがあるのです。
症状が軽くても、状態をきちんと書面で示すことで、学校も安心して対応できます。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
医師に相談する際は、「出席扱いの制度に必要な診断書です」とはっきり伝えることが大切です。
医師側が制度を知らない場合もあるため、こちらから説明しながら依頼するのがスムーズです。
必要であれば、文科省の通知文などを見せながら依頼してみましょう。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
診断書の内容は非常に重要です。
ただ「不登校」と記載されるだけでなく、「家庭での学習は継続できており、支援が効果的である」など、前向きな評価が入ることで、学校側の印象も大きく変わります。
医師との面談の際には、すららでの学習進捗や取り組み姿勢などをしっかり伝えるようにしましょう。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いが認められるためには、単なる読書や市販ドリルのような自習では不十分とされます。
文部科学省のガイドラインでも、「学校教育に準じた水準の教育内容であること」が条件とされており、すららのように教科書準拠の教材で、指導や評価が可能な仕組みがあることが前提となります。
すららはこの条件を満たしている教材ですが、保護者や子どもがその意義を理解し、記録や成果をきちんと提出できるように準備することが必要です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
学校の教科書とリンクしているか、カリキュラムが教科ごとに体系的に構成されているか、評価ができる仕組みがあるか。
この3つが出席扱いの判断基準になります。
すららはすべてを満たしている教材ですが、学校側に説明する際には、それをしっかり示すことが大切です。
学習履歴の提出や、保護者からの報告も丁寧に行いましょう。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いとして認めてもらうためには、家庭学習の“量”も重要なポイントになります。
文部科学省のガイドラインには明確な時間指定はありませんが、多くの学校では「1日2〜3時間程度」が目安として求められることが多いです。
これは、通常の授業時間と大きくかけ離れていないことを示すための目安です。
すららの場合、毎回の学習時間が記録されるため、「今日はどれくらい取り組んだか」が正確に可視化できます。
1回の学習を30分〜1時間程度に設定し、無理のない範囲で毎日継続できるように計画しておくことが、申請成功の鍵になります。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
出席扱いの申請においては、「どの教科に取り組んでいるか」も大きな判断材料になります。
すららは国・数・英・理・社の5教科対応ですが、家庭学習での実施内容が偏ってしまうと、学校側から「授業と同等とは言えない」と判断される場合もあります。
特に理科や社会を後回しにしがちですが、出席扱いを希望するのであれば、全教科にバランスよく取り組む必要があります。
AIによる診断やコーチのサポートを活用し、得意・不得意の偏りを整えながら、幅広く学習を継続することが重要です。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いを維持するためには、学習の継続そのものだけでなく、「家庭と学校の連携」が大きなポイントになります。
すららでしっかりと学習していたとしても、それを学校に報告・共有していなければ評価はされません。
つまり、「どれだけ家庭で頑張っているか」を担任の先生や学校長に“見える化”して伝えることが、出席扱い認定の前提条件となるのです。
そのためにも、月1回を目安に学習レポートを提出したり、電話・メールなどでこまめにコミュニケーションを取ることが大切です。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
学習状況を「家庭内だけ」で完結させるのではなく、学校側とも共有することが必要です。
進捗状況や学習計画、子どもの意欲などを定期的に担任に伝えておくことで、「この子は家庭で学びを継続している」という証拠になります。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららには学習記録をPDF形式で出力できる機能があります。
このレポートを月1回程度のペースで学校に提出することで、学校側も継続学習を確認でき、出席扱いの可否判断がしやすくなります。
印刷して提出しても、メール添付でも対応可能な学校が多いです。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校によっては、出席扱いの継続のために面談や家庭訪問を行うケースもあります。
「なぜ登校が難しいのか」「家庭学習がどのように行われているか」を確認したいという意図があるため、協力的な姿勢を見せることで学校との信頼関係も築きやすくなります。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
面談や書類だけでは伝えきれない日常の取り組みは、メールや電話で随時共有するのがおすすめです。
すららでどんな単元を終えたのか、どんな反応だったのか、学習時間などを簡単に報告しておくと、「しっかり取り組んでいる」という印象を持ってもらいやすくなります。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
出席扱いの判断は基本的には学校長の権限に委ねられますが、一部の自治体では教育委員会への申請・報告が必要になることもあります。
特に長期的な不登校や、特別支援が絡むケースでは、教育委員会が指導や判断を行う場面も増えています。
そのため、事前に担任や教頭先生に「この地域では教育委員会への確認が必要かどうか」を聞いておくと安心です。
また、教育委員会向けに必要な書類のフォーマットや内容についても、学校と連携してしっかり整えていくことが重要です。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会に提出する資料は、内容や形式が地域によって異なる場合があります。
すららの学習レポートや診断書、家庭の学習計画などをまとめる必要があることも。
学校側と二人三脚で準備を進めることで、ミスや手戻りを防ぐことができます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを解説
すららを使って出席扱いを申請する際、「どうやって学校側を納得させるか」という点は多くの家庭が悩むところです。
制度上は条件を満たしていれば認定されるものの、実際には学校ごとに対応や考え方が異なり、うまく進まないこともあります。
そこで今回は、出席扱いを認めてもらうために効果的な「成功ポイント」を4つご紹介します。
どれも実際に出席扱いが認定されたご家庭が実践していた方法であり、すららを活用しながら前向きに学習を続けていることを学校に伝える具体的なアプローチとなります。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
出席扱いの申請がスムーズに通るかどうかは、学校側が「すらら」をどれだけ信頼しているかによって変わります。
まだ導入例がない学校では、慎重になる先生も少なくありません。
そこで有効なのが、「他の学校で出席扱いが認められた事例」を紹介することです。
前例があることで、先生も「うちの学校でもいけそう」と感じてくれやすくなります。
すららは全国の多くの学校で実績があり、公式サイトにも具体的な事例が掲載されています。
それらをプリントアウトして持参するだけでも、説得力が大きく変わります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
たとえば、「〇〇県〇〇中学校で出席扱いになった」「〇〇市ではすららを公式に推奨している」といった情報を伝えると、担任や校長先生も前向きに検討してくれることが多くなります。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すらら公式の「出席扱い実績」ページでは、導入校や実例が丁寧に紹介されています。
PDF化して学校に渡せるように印刷しておくと、説明の際にとても便利です。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
制度上の条件をクリアしていても、出席扱いを認めるかどうかを決めるのは「本人の学習意欲があるかどうか」が鍵になります。
すららのコーチや教材の力だけでなく、「本人が前向きに取り組んでいる姿勢」を学校側にしっかり伝えることが重要です。
そのために役立つのが、「本人が書いた感想文」や「将来の目標シート」などの提出。
また、面談時に本人が同席して、自分の気持ちを伝えるだけでも、印象は大きく変わります。
言葉にしなくても、その場にいること自体が大きなアピールになるんです。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
たとえば、「今日は英語をがんばりました」「テストで〇点取りたいです」など簡単な内容でもOK。
本人の言葉があると、先生の受け止め方も違ってきます。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
話すのが苦手なお子さんでも、親の横でうなずいたり、一言だけでも話すことで、前向きな気持ちを伝えることができます。
とても小さなことが、大きな信頼につながります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いが認められるうえで、最も重視されるのが「継続性」です。
一時的に頑張っても、長続きしないようでは意味がありません。
そのため、無理なく続けられる学習スケジュールを立てることが重要です。
すららでは、専属のすららコーチがついており、お子さんの特性や生活リズムに合わせて、無理のない学習計画を一緒に考えてくれます。
「毎日10分から始める」「週に〇回、復習を入れる」など、具体的で現実的なスケジュールは、学校にも良い印象を与えます。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
どんなに立派な計画でも、本人が続けられなければ意味がありません。
集中力や生活リズムに応じて、無理のないステップから始めるのが成功のコツです。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
コーチは出席扱い制度についても理解しており、学校への報告資料の準備と合わせて計画を立ててくれるため、とても頼りになります。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
出席扱いを申請・継続するうえで、すららコーチの存在はまさに「伴走者」です。
どの単元を優先すべきか、どのようにレポートを作成すれば良いか、さらには学校への提出資料の書き方まで、親では対応が難しい部分をフォローしてくれます。
また、保護者とのやり取りだけでなく、お子さん本人との関係も築いてくれるため、「親子だけで抱え込まない」仕組みとして大きな安心感を与えてくれます。
出席扱いの実績もあるコーチが多く、信頼できるパートナーとして心強い存在です。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
学習進捗レポートのダウンロード方法、学校への説明文の書き方、提出書類の整え方など、出席扱いに必要な事務的サポートも、すららコーチがしっかり対応してくれます。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミ・評判を紹介します
不登校の子どもを持つ保護者にとって「家庭で学習していることが学校の出席扱いになるのか?」は大きな関心事です。
すららは文部科学省が推奨するICT教材として一部の学校で活用されており、条件を満たせば出席扱いとして認められるケースがあります。
実際に利用している家庭からは「学校と連携して出席扱いになったので安心した」「家にいながらも学習を継続できて自信につながった」という声が寄せられています。
一方で「学校によって対応が異なり、必ず出席扱いになるわけではなかった」という口コミもあり、地域や学校ごとの判断に左右されるのが現実です。
ただ、すららを通じて家庭学習を続けていること自体が評価されることは多く、子ども自身の学習意欲や自信の回復につながっているとの声が目立ちます。出席扱いになるかどうかは学校に確認が必要ですが、すららの利用は不登校の子どもにとって大きな支えとなっているのは間違いありません。
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問と回答
不登校の子どもをサポートする中で、「すららを使えば出席扱いになるの?」という疑問はよく聞かれます。
結論から言うと、すららを利用するだけで必ず出席扱いになるわけではありません。出席扱いとして認めてもらうためには、学校や教育委員会との連携が必要であり、学習状況や利用内容を学校側に報告する仕組みを整えることが重要です。
口コミの中には「担任の先生に相談したら出席扱いになった」「学校によっては制度が整っていなくて認められなかった」という声もあり、対応は地域や学校によって異なります。
ただし、すららは文部科学省の出席扱い要件を満たす可能性があるICT教材として認められているため、前向きに検討してもらえるケースが増えています。
実際に出席扱いになるかどうかは、まず学校に確認してみることが大切です。安心して家庭学習を続けるための一歩として、すららを活用する家庭は増えてきています。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すららはうざい」という口コミが出る背景には、主に保護者や子どもが期待した効果と実際のギャップがあったケースが挙げられます。
たとえば「思ったより効果が出るまでに時間がかかる」「子どもが飽きてしまった」といった声です。
ただし一方で、「自分のペースで学べる」「不登校でも出席扱いになるのがありがたい」といったポジティブな評価も多く見られます。
教材は相性もあるため、まずは無料体験で子どもに合うか試してみるのが安心です。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには「発達障害専用コース」という名称はありませんが、発達特性のある子どもにも配慮された無学年式の教材設計と、学習コーチによるサポートが含まれています。
料金については、発達障害の有無にかかわらず共通です。
割引制度はないものの、サポート体制は通常と同様に受けられ、特性に合わせたスケジュール調整や学習方法の工夫もコーチがサポートしてくれるため、実質的に個別対応の学習支援が実現されています。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららのタブレット学習は、一定の条件を満たせば不登校でも出席扱いになることが可能です。
具体的には、学習の継続性・計画性・内容の妥当性が求められ、学習記録レポートの提出や、学校との連携が必要になります。
すららは文部科学省のガイドラインに準じた教材として、全国で数多くの実績があるため、学校側にも説明しやすい点が特徴です。
家庭と学校が連携しやすい環境づくりもサポートしてくれるため、不登校支援に非常に適しています。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららのキャンペーンコードは、入会時の申込フォームに入力することで利用できます。
キャンペーンには「入会金無料」や「1ヶ月無料体験」などの内容があり、時期によって内容が変わるため、申込前に公式サイトや紹介ページでコードをチェックするのがおすすめです。
入力を忘れてしまうと特典が適用されないので注意が必要です。
また、キャンペーンコードは1世帯1回限りの使用が原則で、複数アカウントでは併用できない場合もあります。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを退会するには、まず「解約(料金の停止)」を電話で行う必要があります。
解約後に「退会(アカウントの削除)」を希望する場合は、同じく電話にて申し出をします。
解約だけでは学習記録やアカウント情報が残るため、再開の予定がある方はそのままにしておくのもOKです。
電話のみの対応という点は少し不便に感じるかもしれませんが、丁寧なオペレーター対応でスムーズに完了します。
対応時間などは事前に確認しておきましょう。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららでは、基本的に「入会金」と「月額受講料」以外に追加料金はかかりません。
テキスト購入費やシステム利用料なども発生せず、インターネット環境と学習用端末(タブレットまたはPC)があればすぐに学習を始められます。
端末のレンタルや専用教材の購入義務もなく、家庭で自由に利用できる点が特長です。
ただし、通信環境や端末の整備は各家庭で行う必要があるため、Wi-Fiなどの用意はあらかじめしておくと安心です。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららでは、基本的に「1契約=1名」の学習管理を前提としています。
1人分の受講料で兄弟が共有することはできません。
それぞれのIDで学習履歴や進捗が管理されており、AIが苦手分野の分析や成績向上を支援するため、1人ずつの登録が必要になります。
ただし、兄弟割引制度などが適用されることもあるため、複数人での利用を検討する場合は事前に問い合わせてみるとお得に始められる可能性もあります。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには英語の学習が含まれています。
フォニックス・リスニング・英単語など、小学生でも取り組みやすい内容で、アニメーションや音声を活用しながら自然に英語に触れることができます。
初学者でも楽しく続けられる構成になっているため、「英語が苦手」「習い事に行けない」お子さまでも安心です。
さらに、発音チェック機能や反復練習もあり、基礎から応用までしっかり学べる設計になっています。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららには「すららコーチ」と呼ばれる専任のサポーターがつき、学習の進め方を一緒に考えてくれる心強い存在です。
学習計画の作成や進捗のチェックはもちろん、「どこでつまずいているか」「どうすれば続けられるか」といった個別相談にも対応してくれます。
とくに発達特性や不登校のお子さんには、その特性に配慮した声かけやアドバイスがあり、保護者にとっても大きな支えになります。
親子で伴走してもらえる感覚で、無理なく継続ができます。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材との違いを比較しました
「不登校でも出席扱いになるタブレット教材ってどれがいいの?」と迷っている方のために、今回は“すらら”を軸に、他の人気家庭学習教材との違いをまとめました。
各教材の出席扱い対応の有無、学習記録の提出方法、学校へのサポートなど、気になるポイントを項目ごとにわかりやすく比較しています。
どの教材もメリット・デメリットがあるからこそ、「自分たちの家庭にとって何が一番大事か」を考えるヒントになればうれしいです。
教材選びで後悔したくない方にぜひ読んでほしい内容です。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。
|
16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・注意点・申請手順まとめ
文部科学省が定める「出席扱い制度」により、不登校の子どもでも条件を満たせば自宅学習で出席扱いが認められるようになりました。
なかでも、学習記録の自動生成や継続サポートに強い「すらら」は、この制度に適応しやすい教材として注目されています。
本記事では、すららを利用して出席扱いを申請する際の制度的な背景や流れ、必要書類、注意点などを詳しく解説。
制度の根拠をきちんと理解し、確実に出席扱いを受けるための準備を整えていきましょう。